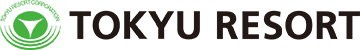「もしもし、馬場さん?次の週末はこちらにいますか?」
ちょうど1年前のこと。
我が家の地区の区長さんから、突然連絡をもらいました。
区長さんには、わたしからお願いごとの連絡をすることはよくありますが、区長さんから連絡をもらうことはほとんどありませんでした。区長さんは実質的な地区の取りまとめ役で、住人の相談窓口から市役所との折衝までをこなす忙しい立場なのです。
うわっ何だろう、何かヘマしたっけ?もしやこないだの中山間地管理の検査で、刈り残しアリの不合格だったのか?と不安がよぎりました。いい想像より悪い想像が先立つとは、素行にまったく自信のない証拠だよな……
区長さんは、ことばを続けました。
「あのね、そこの増間川でモクズガニがたくさん獲れたからね、よかったらお子さんも連れてみんなで、うちに食べに来ませんかね。ちょっとさ、残酷料理ですけどね。滅多に食べられないと思うんでね」。
ぬぬ、お叱りじゃなかった。よかった!
てかむしろ美味しいお誘いじゃないか!
しかも、あの、モクズガニ?たくさん獲れたと?
行かない理由など、ありません。
「次の週末ですか、います!バッチリ三芳にいます。ぜひ伺わせてください!」
モクズガニは、高級食材として有名なあの上海ガニと、ほとんど同じもの。たまに我が家の下の平久里川で見つけると「モクズガニだああああっ!」と大いに喜びます。
野生から食を得る習慣はもう失われつつあるけれど、モクズガニだけは今でも川で獲って楽しむ地元の人が少なくないと聞きます。
電話口で興奮しながら、ちらっと「残酷料理?」と首を傾げたけれどそれもすぐに忘れ、カニ嬉しいな、と楽しみにしていました。
そして、当日。
ぞろぞろとこどもたちを連れ、区長さんの家に遊びに行くと、すでにその「残酷料理」づくりは始まっていました。
庭には、大きな大きな石臼と、重たそうな杵。
そしてガサガサと音のするバケツ。中にはたくさんのモクズガニ。

バケツの中で、元気よく動くモクズガニ。カシャカシャと生きている音がします。
区長さんは「ほれ、こっちがメスで、こっちがオス」とこどもたちに教えてくれました。メスの方が、味が美味しいんですって。大きなハサミを持ち上げて活きのいいオス。基本的に恐怖心や抵抗のないうちの子たちは、「カニかわいい~飼いたい~」と甲羅をなでます。
しかし自らの行く末を察してか、泡を吹くカニ……

俎板の上の鯉、いや、区長さんの手のカニ。ブクブクブク。
「ちょっとね、かわいそうかもしれないけどね」。
一言そう前置きした後、そのカニをぽいと石臼の中に放り込みました。
そして間髪を入れず、杵でぐいぐい潰す。
えーー!!

親戚の方が、調子を合わせて放り込んでいきます。
カニは潰された後も1~2秒は動いていますが、すぐにバラバラになり、茶色い粘土状のものと甲羅のカケラがぐちゃぐちゃに混ざっていきます。
「こうやってね、粉々になるまで潰していくの。形が分からなくなるまでね」
ホイッと放り込んでは潰し、放り込んでは潰す。
こどもたちとわたしは、この様子を呆然と見ていました。
すごい。半分に割って食べるとか、まるごと茹でるとか、そんなものを想像していたんですが、形が分からなくなるまで粉々に潰すとは想定外の外。
わたしから見ると充分粉々になったというレベルでも、区長さんはまだ丁寧に潰していきます。元はカニだったとは思えないレベルになっているのに、手を止めません。
「まだまだだよ。もっと細かくならないと、口当たりが悪いから」。
そうなんですか、とうなずきながらも結局どういう料理になるのか分からぬまま、作業は進行していきます。
頭がクエスチョンでいっぱいの状態ではありながらも、額に汗を浮かべている区長さんの前で涼しい顔をしているのは何とも申し訳ないので「わたしたちもやります!」と木の杵を持たせてもらいました。
いやあ、すっごく重い!

娘は持ち上げるのがやっと、という重たい杵。これでゴリゴリやれば、そりゃあひとたまりもありませんね。
この、泥みたいなものを食べるのかなあ、美味しい身の部分はちゃんとすくえるかなあ、なんかもったいないなあなんて思っていると、「よし。そろそろだっぺ」と、ようやく区長さんの手が止まりました。大きな身体が、ふう、ふう、と荒い息で揺れます。
そこへ奥さんが味噌を差し出しました。「こんなもんかねえ」と、一すくいして投入。大胆に、臼の中に直接ボタッと入れるかんじです。

量は、あくまで目分量。
そもそも茶色いので、味噌を入れてもあまり変化がありません。
これをよく混ぜた後に、「おい、水」の声でペットボトルが差し出されました。じゃぼじゃぼじゃぼ、と水も投入。
薄まると、まるで泥水。
これを竹のザルで濾して殻をすっかり取り除き、鍋にうつします。

「いろいろ使ってみたけれど、竹のザルがいちばんうまく濾せる」とのこと。
「さて、じゃあこれを、台所に持ってくから」と場所も移動。
なにか具を入れて煮るんだろうか?と、思いきや、そのまま鍋を火にかける区長さん。
「いい?よく見てて。温まってくると、出てくるから」。
出てくるから?何が?
もう、頭の中は疑問だらけです。
よく分からないけれど、とにかく泥水のようなものが満たされた鍋をじーっと見続けるわたしたち。まさか、あの粉々に砕かれたカニの怨霊が早速出てくるとか?
すると、湯気の立った鍋に異変が起きました。
ごぼ、ごぼ、と湧き上がる音と一緒に、白いかたまりが浮いてくるのです。
汁の中に溶けていたタンパク質が熱されて固形になった模様。
ごぼ、ごぼごぼ。
はじめは卵の白身のようなものが控えめに沸きのぼってきていたのですが、そのうち、大きな塊がゴボッ!と出てきました。
ゴボッ、ゴボゴボゴボッ!

一気に塊が浮き上がります。しかしハードなアク?と見えなくもない。笑
うわあ!とこどもたちから声が出ます。
いつの間にか泥水は透明の澄んだ汁になり、ふわっとした塊が鍋一面を覆っていました。ほとんどマジックショーのようです。
「さあ、できた。口に合うかはわかんねぇけどな」
出来上がりを待つみんなのところに戻り、その鍋と、炊き立てのご飯をドンと置くと、アツアツのものをお椀によそってくれました。

カニまるごと入っているふわッふわを、ふーふーして食べます。
すごい…!美味しい!
カニが、濃い!
こんな料理、食べたことがありません。おぼろ豆腐のようなふわふわの塊はとにかく風味が素晴らしく、カニの身をせせって食べるよりずっとボリューム感があります。味噌はふわふわの塊の中に入っているようで、塩加減が絶妙。透き通った汁は実に上品な味です。
これは、‘ズガニ汁’ ‘カニコ汁’と呼ばれる、このあたりの郷土料理だとのこと。
「昔はね、どこの家でもやってた料理ですよ。ちょっと残酷料理だけどね、こうやって食べるのが一番、無駄がないでしょう。殻以外はぜーんぶこの汁の中に入っちゃうんだから。でもね、こうしてみんなで集まってつくらなきゃ、できない料理でしょ。だからもう今では、このあたりだとうちくらいしかやる家はないの」。
確かにまったく無駄がない上に、心も体も濃いカニの風味に包まれるような素晴らしい食べ方です。
これだと潰されたカニにも申し訳が立つ気がしてきます。
みんなでお正月のように集まり、庭で鍋を囲んで、やっぱりうまいねえ、お父さんの匙加減だから教えられないねえ、なんていいながらハフハフ食べる。よく晴れた秋の日の、実に贅沢な時間。
わざわざ集まってでも食べたいと思うのですが、やっぱり手間暇がかかることで失われていく郷土料理なのかもしれません。
次々と石臼の中でつぶされていくカニを「うわぁ……」と呆けたように見つめていたこどもたちも、「ママ美味しいね」と夢中で食べていました。、一部始終を一緒に見て、体験できて、本当によかった。
命を大事にしよう、食べ物は命だよ、ということを伝えるのは、なかなか難しいことです。
命を粗末にするのはもってのほかですが、逆になんでもかんでも「かわいそう!」と安易に同情するのも少し違うんだよ、というニュアンスも分かってもらいたい。
また同時に、あまり残酷な場面を見せるのは教育的にどうなんだろう、とドキドキする部分もあったりするワケです。「生と死は、表裏一体」という事実を、頭と心で同時に理解するには適切なプロセスを踏む必要があります。
実は昔むかし、息子のニイニは平久里川で獲ってきたエビを飼っていたのですが、「なんかヘンだと思う。エビ飼ってるのに、食べるエビは買ってくるって。獲ったエビを食べてみたい」と言い出したことがあるんです。
川でつかまえた後、一時的にプラケースに入れておきます。そこまでは、ペットのエビと同じ扱いでした。ところが、そこから網ですくい出して台所に持っていくところで、突如「食べ物」という扱いに変わります。ニイニはそこで突然泣き出して、「一瞬で死ぬのは、茹でるのと、揚げるの、どっち?」と聞いてきました。多分油で揚げた方がより苦しまないんじゃないかな……と言うと、大泣きしながら油に入れて、揚げました。

まだ小さかったニイニ。自分で決断したのに、その瞬間は涙が止まりませんでした。
ペットになりうるエビが、ジュワッと、本当に一瞬で揚がりました。
取り出すと、とてもいい匂いがしました。
これを口に入れた息子は「お、お、おいしい!」と泣き笑い。それは、いつも食べているエビの味そのものだったのです。
今回のズガニ汁の体験もまさに、命をいただくプロセスでした。オトナたちはただ乱暴に潰しただけではなく、ありがとうという気持ちで丁寧につくっていました。それを見て、やらせてもらって、いっしょに食べたこどもたちには、きっと幾ばくかの思いが残るだろうと思います。
それにしてもあまりにも美味しかった、このズガニ汁。
できれば多くの人たちと共有したいと思い、つい先日、BSプレミアムの『晴れときどきファーム!』という番組に出演した際、これをみんなでつくって食べることにしました。
区長さんにも、美味しいお米を提供してくださったほんまる農園の本間秀和さんにも登場いただきました。

金曜の夜、南房総に到着してすぐ番組が始まり、BSのうつるテレビのある小出さんちに転がり込んでみんなで見ました。
うわ!美味しい!と、出演者のみなさんに喜んでもらえて、スタッフのみなさん全員にも食べてもらえて、区長さんはとても喜んでいました。わたしも、とても嬉しかった。
手間はかかるけれど、できれば未来に失われて欲しくないものがあります。
ならば、伝えられた人が、伝える立場に立つ他ありません。みーんなで感動して、みーんなで記憶に留めれば、どこかに一筋の未来が生まれるのではないかな、と思っています。