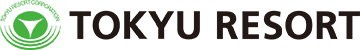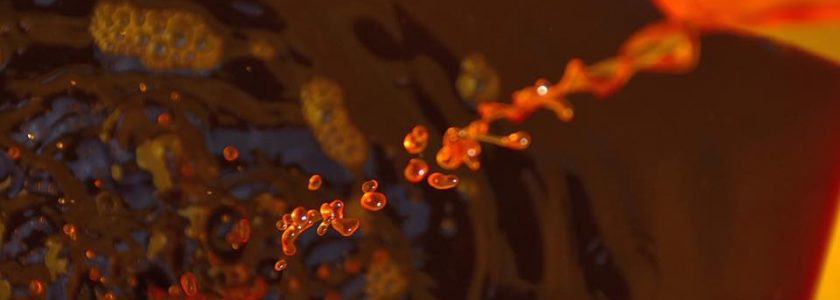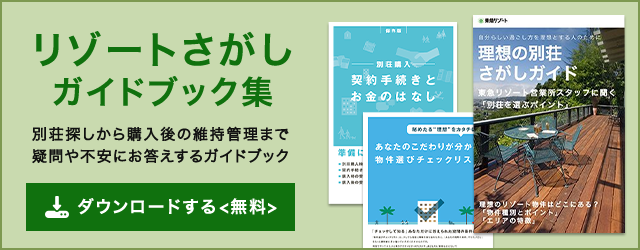ふと漂ってきた風に、湿ったような甘酸っぱいような香りを感じて、身体の中の切ない系ボタンがぽちっと押されること、ありませんか?
春ですね。
365日変わらず生活しているにもかかわらず、何となく春は特別。「そろそろいいよ」と耳元でささやかれ、新しく外に繰り出すときの期待と不安がざわっと心に立ち上がります。
今のところ花粉症になっていないわたしは、(涙目で過ごす家族を横目に)春の風に触れるたびにセンチメンタルになっています。
ったく、毎年毎年、春には気分が揺さぶられるよな。

ぱっと開く一瞬手前の、このかんじ。
最近、この“気分”ってやつの正体を考える機会がありまして。どうも春のせいだけでもないらしい。
人の気分は脳内の神経伝達物質によるものだというのは何となく分かりますよね。ストレスを感じるとお腹をくだす、といった「脳から腸」への働きかけがあるのも実感するところです。ただ、それに加え、幸せホルモンともよばれるセロトニンは腸でつくられているため、腸内を整えることで脳に影響を与えるという「腸から脳」の働きかけもあるそうな。
気分よく過ごそうと思ったら、腸を大事にしようよ!ということらしい。
つまり、春はとくに気分の変動が激しいし、そしたら腸にいいものを食べようじゃないか!と思うのが吉。腸にいいものと言えば、発酵食品ですよね。巷では常識なのかもしれないけれど、わたしはお仕事で知り合った発酵デザイナーの小倉ヒラクさんから、「発酵食品を食べるのは身体だけでなく心にもいい」と教えてもらってへえええ~~と思いました。
発酵食品だったら、このめんどくさがりやのわたしも、ちょっとはつくってます。糠漬けとか、甘酒とか、ヨーグルトとか。だって簡単なんだもん。ほんのちょっとだけ人間がサポートすれば、微生物がでんぷん質やたんぱく質を分解してアミノ酸や糖質をつくり出して、美味しく身体にいいものに変えてくれる。微生物が勝手にそうしてくれるんだから。
・・・・・・そう、あと醤油ね!醤油もつくってます。
春の馬場さんちといえば、醤油です。去年も書いたとおりですね。
だいたいさ、ほっくほくの麹に、塩を足しただけのコレが、

これに水を足すだけ。
1年かけて発酵することで、醤油になるんですよ。

1年後。もろみの状態です。
自分の眼には見えないだけで、このもろみの中にはいーーーっぱい微生物がいて、せっせせっせと働いているなんて、実に興味深い話です。土の中にいる虫たちにキャア!となる人はいっぱいいて、イナゴとかハチノコとか食べますかというとキャアアア!となる人はさらにいっぱいいるけれど、可視化されていなければ気にならないで「身体にいいよね」と食べられる不思議。笑。

さも、昔からこの状態だったような。すました顔してるしね。
さて、2017年3月から2018年2月まで東京の家で世話をしてきたこの馬場さんちのもろみは、いつものように幼馴染や近所の友人たち、ご縁のあった方々、搾り職人のてっちゃん師匠をお招きして南房総の家で搾りました。
初めての年は、搾りの前の晩眠れないくらい緊張したものですが、今年はもう3回目。準備も手順も分かっていて余裕だろうと思いきや、、、やはり緊張するんですね。上手くできたかどうか。
今年は夏に雨が多かったこともあり、しっかり高温で発酵させられたか不安だったし、1度カビがうっすら上がったこともあったしね。みんなを呼んで搾る手前、大失敗だったら恥ずかしいしさ。

楽しそうにしている彼らが、「え、、今年はちょっと、、、」となったらと思うと。
そんなわたしとは裏腹に、搾りメンバーはわいわいとうるさい。
てっちゃん師匠が「今年はやや色薄い気がしますね」と言うと「たしかにちょっとね」とまゆをひそめ、「香りはいいですね!」と言うと「まあ、そうかもね。香りはいい」とソムリエのような訳知り顔でうなずくんです。どういう態度でしょう。
お湯を足して醤油の濃度を決める、という大事な局面でも「どうですか?こんなもんでいいですか?」とオーナーであるわたしにてっちゃんが聞いているのに「ちょっと濃いかな」「こんなもんじゃないか」などとひそひそ。
もう!
みんな毎年来ているもんだから、目も肥え舌も肥えちゃってさ。
うちの醤油を好き勝手にジャッジして!笑。

でも最後はオーナーに責任を押し付ける。「この濃さでいい、って言ったのはみおりさんだよね」みたいな。笑。
とはいえ、この時間は、なかなかに幸せです。
薪をくべてカマドでお湯を沸かしたり、もろみをかきまぜたり、交代で搾りをがんばったり、タイミングを見てランチの用意を始めたりとそれぞれが役割を見つけて手を動かしているうちに、最初はばらばらだった人たちが自然と打ち解けていく時間が好きなんだと思います。
何より、手持ち無沙汰で気まずくなる心配がない。あと、名刺交換もない。誰が何なのかよくわからないけれど、ともかくみんなの最大の関心事は醤油の出来栄えで、隣りの人とあーだこーだ言いながら笑っているとすごくリラックスします。いつもは取っ払いづらい垣根が、短時間で消滅するのは不思議です。
「搾りながらつながる」って、いいもんです。

体力のある若者がいると、本当に助かります。

お小さい方たちもそれなりに。順番が終わるとどっかいっちゃうけどね。
房総での友人(東京と君津の二地域居住から移住にシフト)が、わたしの小学生からの幼馴染(東京と一宮の二地域居住)に、こんなことを話していました。
「このへんの仲間はしょっちゅう集まって、日中はDIYで一緒に家を直して、夜宴会しているんですけどね。以前、あそこにいるおじさんが酔っぱらって転んで、目を強打してひっくり返っていたんですよ。みんな大慌てでね。お酒の飲めない自分が同伴して夜中に病院に連れていったんですけど、『ご家族の方は?』と病院から聞かれても、家族が誰なのか知らないし、だいたいお互いの住んでいるところも仕事も知らない。すっごく親しい気がしてたけど、よくよく考えてみたらこいつ誰だって(笑)」
幼馴染はその話に聞き入っていました。「分かります……その距離感の居心地の良さがあるんですね。焚き火をする仲間と、同じだな」と。
どうもわたしは、南房総にいる間にそうした人間関係が普通に思えるようになってしまっていましたが、確かに、生い立ちや社会的立場をほとんど知らないのに心を許している仲間がいます。宴会の時に話すのは、その日にした作業の話と、明日は何やろうかという話。それからたまに、地域の未来の話。たまにぽろっと勤め先の話が出てくると、「え!そんなことやってる人なの!」とびっくりして笑ったり。
その人をより知るための情報として、あるいは距離感を間違えないための情報として、名刺交換や自己紹介をしますよね。それが、一緒に手を動かしながら過ごしていると、その人についていろいろと理解できてしまうし、信頼関係もできてしまうため、名前以外は知らなくてもあまり気にならない。(ちなみに、その大怪我の一件のあと、彼らは一応「こういう者です」と名刺交換をしたそうですけどね。笑。)

ここもそう。何となく居合わせていますが、東京の人、二地域居住の人、農業を学ぶ人、教える人、いろいろです。

こどもはこどもで、初顔合わせでも楽しそうに遊んでいました。特に好きなのが、敷地内軽トラドナドナ。
それにしても、搾りたての醤油は美味しいです。
特に美味しいのは、搾りが進み、もろみがぎゅっとつぶれてうまみ成分が出てくる後半の醤油です。
このスペシャルな部分は、ほんの少量だけ、火入れせずに生醤油として確保します。常温だと発酵が進んでしまい日持ちがしないものですが、酵母菌などが生きたままなので身体によく、味も透き通っていてお刺身や卵かけごはんによく合います。

昼時になったら、一層人が集まってきました。醤油に合う一品持ち寄りがルール。

ローストビーフに直接生醤油をかける子。

搾ったときの醤油の粒が美しい。地元の小出さんがこれを「醤油の妖精だァな」と言ったら、こどもたちが目を輝かせていました。
あとは、いい塩梅に火入れをして保存可能な状態にします。
火入れの際、「塩ボーメ」という塩分濃度測量計で測るんですが、今年はちゃんと合格範囲の真ん中に!ああ、うまくできてたんだ、とすごくほっとしました。

いい醤油が搾れて、本当によかった。
売っているものより美味しいとか、どうとか、そういうのは個人の味覚にお任せしますけどね(わたしは美味しいと思う!)、春のとば口に立ったとき、そろそろ醤油の時期だっけかなとみんなが思い出し、啓蟄のようにごそごそと集まって、搾る。それだけでいいんだと思います。どこでも何でも買えるご時世に、わざわざこんなことを毎年するのは、「手づくりは尊いことだぞー。こういう文化を絶やすなー」という概念の問題じゃなくて、単純に自分にとって価値のあることだからなんです。
初回から全参加の親友は、「醤油は買うものではなく、搾るものだと思っています」と言い切っていたし、てっちゃん師匠は「醤油づくりは大事にしたいことだけれど、“特別なこと”にはしたくない」と言っていたしね。

今年の面々。よき面々。
最近は微生物のおかげで身体も心もそこそこ調子いいし、ちょっとめんどくさいけど、今年も麹を手に入れよう。
また、新しい醤油を、育て始めよう。